PBXとは? | 仕組みや特徴、選び方、ビジネスフォンとの違いをわかりやすく解説

PBXについて知ってますか?
この記事では「PBX」について解説しています。
結論、PBXはシステムを理解して自社に合ったものを導入することが重要です。
PBX導入を検討する際、知っておきたい「PBXの種類」をまとめたので、ぜひ見ていただければと思います。
その他にも、「ビジネスフォンとの違い」や「主な機能」、「PBXの選び方」についても説明していますので、この記事を読んでPBX導入の参考にしていただければ幸いです。
PBXとは電話交換機のこと

PBXとは、「Private Branch eXchange」の略称で、電話交換機を意味します。
複数の電話回線を集約し、内線同士の接続や外線と内線の接続をコントロールする役割を果たしています。
企業やコールセンターなどで導入されている仕組みです。
ほとんどの企業は、代表電話番号にかけると、まずPBXへ繋がります。
近年はLANと統合するタイプのIP-PBXやクラウドPBXなども登場しています。
IPネットワークを利用し、より高度な機能を備えていることから、今後ますます導入数が増えると予測されるPBXです。
PBXの基本的な機能

PBXは、5つの基本的な機能があります。全て業務効率化や顧客満足度の向上に繋がるものばかりです。
- 発信者の制御
- 内線同士の通話機能
- スマートフォンなどへの転送機能
- 代表番号宛の着信接続
- パーク保留
発信者の制御
PBXは、発信者の制御ができます。直通と内線番号の紐付けができるからです。
- 代表電話番号
- 部署ごとの直通番号の管理
これらの機能を使えば、営業部の直通電話と営業部の内線番号を紐付けることで、直通番号宛にかかってきた電話を営業部へ繋げられます。
発信時も同様で、営業部の内線電話機から外部へ発信すると、相手には営業部の直通電話から着信しているように設定できます。
内線同士の通話機能
PBXでは内線同士の通話機能もできます。以下が代表的な使い方です。
- 内線同士の通話
- 外線を他の従業員の電話へ転送
外線ではないため、通話料が発生しません。更に、拠点間接続をすれば、遠隔地であっても内線で通話可能です。
通信コストを大幅に下げられる機能と言えるでしょう。
スマートフォンなどへの転送機能
PBXには、スマートフォンなどに電話から転送する機能があります。
外出中に、顧客から営業担当宛に電話がかかってきた際に活躍する機能です。
- 不在転送
- 話中転送
- 着信選択転送
- 応答遅延転送
- 圏外転送
- 保留転送
転送方法は、様々なタイプがあります。
スマートフォンに転送すると、スマートフォンを社内の内線として使えます。
外出先からも通話料を気にせず社内へ電話できる点がメリットです。
代表番号宛の着信接続
PBXでは、代表番号宛に電話があった際、あらかじめ作成しておいたグループの電話機へ繋げる機能があります。
受け取る電話機に優先順位をつけられます。
例えば、話し中の場合は別の電話機に転送するといったことも可能です。
パーク保留
パーク保留は、保留にした通話を他の電話機で引き継げるようにする機能です。
本来、保留はその電話でしか通話を再開できません。
パーク保留なら、他の電話機で保留を解除して通話を再開できます。
PBXに接続されている全ての電話機で受けられるため、違う部署で電話を取っても速やかな対応が可能です。
社内で対応可能な人間が対応できることもあり、顧客満足度向上にも期待できます。
PBXとビジネスフォンの違い

PBXと似ているものでビジネスフォンがあります。
どちらもビジネスにおいて利用されている電話サービスであり、以下の点で共通しています。
- 1つの回線を複数の電話機で共有する
- 外線の発着信
- 内線同士の通話や転送
主な機能は同じです。両者を比較すると、以下の表のようになります。
| 特徴 | PBX | ビジネスフォン |
|---|---|---|
| 複数拠点での利用 | 距離的に離れた別オフィスや拠点とも接続可能 | 同一拠点かつ同じフロアのみ利用可能 |
| 接続台数 | 数千台以上 | 最大で数百台程度 |
| システムの安定性 | 停電やシステム障害発生時も利用可能 | 別途機器を追加する必要あり |
| 初期費用 | 数百~数千万円程度 | 数十万~数百万円程度 |
複数台で利用可能か
PBXとビジネスフォンは、複数拠点で利用可能かどうかが大きな違いです。
ビジネスフォンは、同一拠点かつ同じフロアでなければ利用できません。
一方のPBXでは、別の階や遠距離のオフィス・拠点でも利用できます。海外拠点でも利用可能なため、グローバルに展開する企業では通信コストを気にせずに通話できます。
企業規模に合わせて選択すると良いでしょう。
接続台数が違う
ビジネスフォンは、従来通りのアナログ的な接続方法にしか対応していません。
どうしても接続可能な電話機の台数に限界があります。
カバーできるのは、最大でも従業員が数百人程度でしょう。
一方のPBXは、デジタルで処理することもあって、数千台以上の接続も可能です。従業員が千人を超える企業やコールセンターでは、PBXの方が有利と言えます。
システムの安全性
ビジネスフォンは、システムダウンすると使えないデメリットがあります。
システムダウンしても使うなら、別途機器を追加しなければなりません。
PBXは、システムを二重化しておけば、1つのシステムがダウンしてももう一方のシステムを稼働させればそのまま使えます。
更に内蔵バッテリーを搭載することで、停電時であっても1日程度は稼働します。
システム障害や停電といった災害に強い点は、PBXならではと言えるでしょう。
初期費用
初期費用の面でも、両者は大きく違います。
一般的にビジネスフォンの方が安い傾向にあります。
数十~数百万円のコストで導入できるからです。
対してPBXは、電話機に加えて構内交換機と工事費が必要になるため、高額になります。総額で数百~数千万円のコストになることも。
近年はIT技術の進歩によって、初期費用を抑えられるクラウド型のPBXも登場しています。
ランニングコストはかかりますが、初期費用を抑えるなら検討したい方法です。
PBXは3種類ある

一口にPBXと言っても、3種類あります。
それぞれ特徴が異なるため、用途に合わせて選びましょう。
- レガシーPBX
- IP-PBX
- クラウドPBX
レガシーPBX
レガシーPBXは、旧来タイプとも呼ばれるPBXです。
企業の構内に、電話線と電話機といった物理的な装置を設置します。
- 外線との発信・着信の制御
- 内線同士の通話機能
- 代表番号着信機能
- 転送機能
- パーク保留機能
これらの機能は全て使えます。
インターネット回線がなくても内線と外線を利用できるので、サーバーダウンや停電といった影響を受けません。
ただし電話線を使うことから、設置場所は電話線の長さという物理的な制約を受けます。
IP-PBX
IP-PBXは、IP網を使ったPBXを指します。
電話線ではなく、IPネットワークを使って通話を行います。
専門業者による工事が不要で、社内LANに接続するだけで設定できる点が魅力です。
各種設定もパソコンの画面上でできます。
インターネット回線を使うため、複数拠点の接続も可能です。
場所の制限がなくなり、全ての拠点を内線で接続でき、以下の2種類に分けられます。
- ハードウェア型:動作環境が安定し、セキュリティ面で安全。コストは高め
- ソフトウェア型:外部システムとの連携・拡張性に優れる。コストは控えめ
セキュリティか拡張性かのどちらを優先するかで選ぶと良いでしょう。
IP-PBXのメリット
IP-PBXはIPで接続するPBXです。
以下のメリットがあります。
- 席を変えても電話番号が変わらない
- パソコンと連携できる
- 拠点ごとのPBX設置が不要
- 拠点間の内線化によって通話料金を削減できる
- パソコンで簡単に管理できる
- スマートフォンを内線化できる
IP-PBXならではのメリットは、非常に大きいと言えます。
IP-PBXでできること
IP-PBXは、レガシーPBXと比べて、できる業務が増えています。
特に以下の点は、業務効率化に役立つ機能です。
- 通話内容をパソコンに記録できる
- 留守番電話をメールで送信できる
- 電話帳から発信できる
- パソコンやスマートフォンを内線端末として利用できる
- 発信相手の情報をポップアップで表示できる
- ビデオ通話
- 通話内容や履歴のバックアップが取れる
- FAXをペーパーレス化できる
このように、インターネット回線を使うからこその機能が多くあります。
クラウドPBX
クラウドPBXは、近年注目されているPBXです。
構内にPBX機器を設置するのではなく、クラウドで電話交換機能サービスを使います。
IP-PBXと比べて、以下のメリットがあります。
- 初期費用・運用コストの削減が可能
- 運用業務の削減
- 拡張が容易
- 必要な機能のみを利用できる
- モバイル端末と連携できる
- 工事が不要
- 在宅勤務の従業員も利用可能
- 海外の拠点とも通話可能
中でも初期コストを大幅に削減できる点に注目です。
構内に機器を設置する必要がないため、事業所の移転や拡大にも柔軟に対応できます。
基本的な機能はIP-PBXと同じです。コスト面でIP-PBXの導入が難しい場合に選択すると良いでしょう。
PBXよりもビジネスフォンの方が良いケース
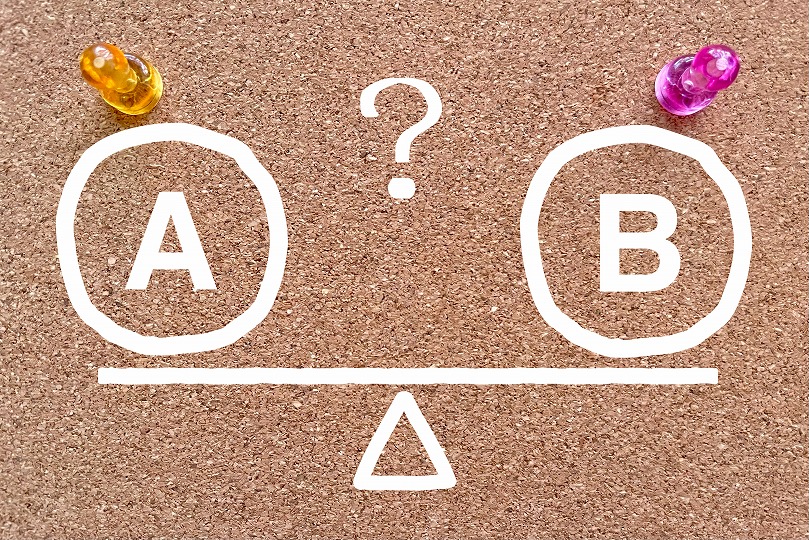
PBXはただ導入すればいいものではありません。
企業によっては、PBXよりもビジネスフォンの方が良いケースも多々あります。
PBX導入はコストもかかるため、自社の状況に合わせて選択してください。
特に以下の状況では、無理にPBXを導入する必要はありません。
- 拠点が一箇所である
- 従業員・回線が少ない
- 外線に関連する機能を重視したい
PBXだとオーバースペックとなり持て余す可能性も慎重に検討しましょう。
PBXの選び方

PBXには選び方があります。
3種類とも常に進化し続けていることもあり、いざ導入しようと考えると決めあぐねる可能性もあるでしょう。
導入後に後悔しないためにも、以下の点は意識してください。
- コスト
- 設置工事
- 機能のカスタマイズ性
- セキュリティとBCP対策
コスト
PBX導入において最も重要視したいポイントがコストです。
それぞれ以下のように違います。
- レガシーPBX:導入コストや管理費用が高め
- IP-PBX:予算を抑えるならソフトウェア型
- クラウドPBX:導入・管理コストが抑えられるが、月額費用がかかる
初期費用が抑えられるクラウドPBXは、利用し続ける限りランニングコストがかかります。
企業規模が大きくなるほど費用面も大きくなることもあるので、結果的にIP-PBXの方が費用を抑えられる可能性もあります。
設置工事
PBXは、設置工事にも時間・コストがかかります。
配線部分はPBXの根幹とも言えるので、必ず確認してください。
- レガシーPBX:既に配線がある
- IP-PBX:既に配線がある
- クラウドPBX:配線がない
既に配線がある場合は、新たに工事をする必要がないので、そのまま使えるレガシーPBXかIP-PBXがオススメです。
一方、配線がない場合やリモートワークに対応したい場合は、配線工事を必要としないクラウドPBXがオススメです。
機能のカスタマイズ性
PBXを選ぶ上で、機能のカスタマイズ性も意識したいポイントとなります。
インターネットを通して必要な機能だけをカスタマイズできます。
- 回線数の増減が考えられる
- オプション機能を追加するかもしれない
- スマートフォンやタブレットを内線化したい
このような場合は、タブレットPBXを選びましょう。
セキュリティとBCP対策
企業にとってセキュリティは重要な問題です。
セキュリティを重視する場合は、インターネットに接続しないIP-PBXを選んでください。
クラウドPBXはインターネット接続となるため、ハッキングといったリスクが生じるからです。
他にも、以下の番号がクラウドPBXで使えません。
- 110番
- 119番
一方で、BCP対策として地震や災害時のインフラを考慮すると、クラウドPBXに強みがあります。
PBXを正しく理解して自社に最適なシステムを導入しよう

PBXは、複数の電話回線を集約し、内線同士の接続や外線と内線の接続をコントロールする電話交換機です。
導入することで電話に関連する業務を効率化できますが、初期費用は高いものがほとんどです。
企業によってはビジネスフォンでも問題ないところもあるため、自社に合わせて選ぶと良いでしょう。PBXは3種類に分けられますが、それぞれ得意とするものが違います。
コストや機能など様々な面から総合的に判断し、自社に合った最適なシステムを導入してくださいね。

