パソコンを利用監視する方法は?注意点とツールの選び方を解説

企業のセキュリティ強化や生産性向上のため、パソコンの利用監視を検討する企業が増えています。
とはいえ、具体的な監視方法や注意点がわからず、知りたい担当者も多いでしょう。
この記事では、パソコンの利用監視の方法から確認できる項目、注意点、監視ツールの選び方まで、企業が知っておくべきポイントを詳しく解説します。
パソコンの利用を監視する方法

パソコンの利用監視は、おもに専用の監視ツールの導入により実現できます。
これらのツールは、従業員のパソコンに専用ソフトウェアをインストールし、操作ログを収集・記録する仕組みをもちます。
監視ツールの活用により、テレワーク環境下でも従業員の勤務実態を適切に把握でき、生産性向上や内部不正対策につなげることが可能です。
パソコンの利用監視ツールで監視可能な項目

パソコンの利用監視ツールを導入すると、企業は従業員の業務状況を詳細に把握できるようになります。
おもな監視項目は、以下のとおりです。
- インターネットの使用状況
- 電子メール
- ソフトウェアの使用状況
- キーロガー
- ファイルとデータのアクセス
- チャットログ
これらの監視項目により、企業は業務効率の向上とセキュリティリスクの低減を同時に実現できます。
インターネットの使用状況
従業員のWebサイトやアプリケーション使用状況の監視は、情報漏えいや業務効率化の観点から重要です。
パソコンの利用監視ツールを活用すると、以下のようなインターネット利用状況を確認できます。
- アクセスしたWebサイトのURL履歴
- 各Webサイトでの滞在時間
- ダウンロードファイル、アップロードファイルの情報
- SNSやオンラインゲームなど業務外サイトへのアクセス
なかには、業務に関係のないWebサイトへのアクセスを検知すると、自動的にアラートを発する機能が搭載されている監視ツールもあります。
管理者は問題のある利用をリアルタイムで把握でき、適切な指導をおこなうことが可能です。
また、特定のWebサイトへのアクセスを制限する機能をもつツールもあります。
これにより、セキュリティリスクの高いWebサイトや生産性を著しく低下させる可能性のあるWebサイトへのアクセスを未然に防ぎやすくなるでしょう。
電子メール
パソコンの利用監視において、企業が監視可能な電子メールの項目は以下のとおりです。
- 送信元、送信先
- 件名、本文
- 日時
- 添付ファイルの有無
- 送受信データ量
業務用メールアカウントで送受信されるすべてのメールは、会社のサーバーに保存されるため、技術的には完全な監視が可能です。
しかし、監視の目的や手段、その態様などを総合的に考慮し、監視される側に生じた不利益と比較したうえで、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合は、プライバシー権の侵害となる可能性があります。
そのため、電子メールを監視する場合は、その目的を明確にし、過度に詳細な内容まで監視しないことが重要です。
私的利用の程度が著しい場合に限定するのがよいでしょう。
ソフトウェアの使用状況
パソコン上で動作するソフトウェアの使用状況を監視すると、業務効率や生産性を可視化できます。
利用監視できるおもな項目は、以下のとおりです。
- アプリケーションの起動・終了時刻
- 使用頻度と利用時間
- 実行ファイル情報(プログラムファイル名、バージョン、言語など)
- ユーザー別の利用状況
これらの情報を収集・分析すると、不要なソフトウェアライセンスの削減や、業務に必要なツールの導入判断などに役立てられます。
キーロガー
キーロガー(Key Logger)とは、ユーザーがキーボードで入力した文字や操作を記録するソフトウェアまたはハードウェアのことです。
本来は、ソフトウェア開発時のデバッグ作業や端末の不正使用ログの収集など、正当な目的で使用されるツールですが、パソコンの利用監視においても活用されています。
企業でキーロガーを利用管理する目的は、従業員の作業効率の把握や不正行為の防止などです。
キーボード入力の監視により、どのアプリケーションでどのような作業をおこなっているかを把握でき、業務の透明性を確保できます。
ただし、プライバシーへの影響が大きいため、監視する場合には十分な注意が必要です。
ファイルとデータのアクセス
パソコンの利用監視において、ファイルとデータのアクセス状況を把握することは、情報セキュリティ対策において重要な要素です。
監視できるおもな項目は、以下のとおりです。
- ファイルの作成・編集・削除の日時
- アクセスしたユーザー名、パソコン端末情報
- 共有フォルダへのアクセス状況
- 外部記憶媒体(USBなど)への書き込み履歴
監視により、重要ファイルへの不正アクセスを検知し、機密情報の保護に役立てられます。
また、データの持ち出しを早期発見し、情報漏えいの防止につなげられるでしょう。
トラブル発生時には、証跡の確保により原因究明に活用できます。
特に機密情報を扱う部署では、ファイルアクセスの監視により、権限のない従業員による不正なアクセスや、大量のデータコピーなどの異常な動きを検知できます。
また、クラウドストレージの利用が増えるなか、オンプレミスのファイルサーバーだけでなく、クラウド上のファイルアクセスも監視対象に含めると、より包括的なセキュリティ対策が可能です。
チャットログ
VoIP(ボイスオーバーインターネットプロトコル)などのビジネスチャットツールの利用履歴も、パソコンの利用監視における重要な監視対象です。
監視できるおもな項目は、以下のとおりです。
- メッセージの送受信履歴
- 添付ファイルの送受信記録
- チャットルームへの参加履歴、退出履歴
- メッセージの編集履歴、削除履歴
ログ取得により、業務時間内の適切な利用確認や機密情報の不正な共有防止、コミュニケーションの証跡管理が期待できます。
特にテレワーク環境では、対面でのコミュニケーションが取れない分、重要な役割を果たすでしょう。
パソコンの利用を監視するときの注意点
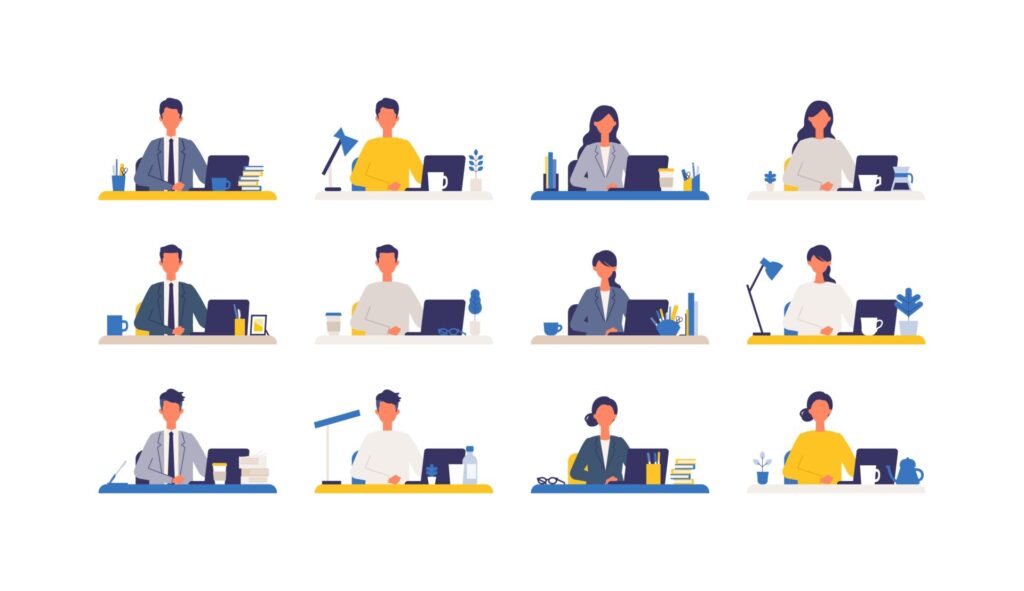
企業におけるパソコンの利用監視は、業務の効率化や情報セキュリティの向上に有効です。
しかし、導入・運用にあたっては、従業員のプライバシー保護への配慮や過度な監視によるモチベーション低下のリスクなどに注意が必要です。
以下で詳しく解説します。
従業員のプライバシー保護への配慮
企業が社内パソコンのログ監視をおこなうときは、従業員のプライバシー権に十分配慮する必要があります。
社内パソコンは企業の所有物であるものの、従業員は通常、業務中に送受信するメールや閲覧するWebサイトの内容を第三者に見られることを想定していません。
過去には、企業による私用メール調査の適法性が争われた裁判例「日経クイック情報事件」がありました。
この事件では、企業がほかの社員を誹謗中傷するメールの送信者を特定するために従業員のパソコンを調査したところ、私用メールの存在が明らかになっています。
ところが、当該従業員により、企業の調査行為がプライバシー侵害や名誉毀損に当たるとして訴えられました。
判決では、企業秩序維持のための調査の必要性が認められ、違法でないと判断されました。
一方で、調査の必要性を欠く場合や、調査の態様が社会的に許容できる限度を超えている場合は違法となる可能性が出てきます。
そのため、企業が利用監視を実施する場合は、業務上必要な範囲に限定し、個人的な行動の詳細な追跡は避けるべきといえます。
また、収集したデータは目的外使用を禁止し、アクセス権限を制限するなど、適切な管理体制を整えることが大切です。
監視実施の事前告知と同意取得
パソコン利用監視の事前告知と同意取得は、従業員のプライバシー権と企業の管理権のバランスを取るうえで極めて重要な手続きです。
従業員に対する事前告知では、以下の内容を明確に伝える必要があります。
- 監視をおこなう目的(情報漏えい防止、業務効率化など)
- 監視対象となる項目(インターネットの閲覧履歴、メール、ソフトウェア使用状況など)
- 監視データの保管期間と利用範囲
- 監視を実施する時間帯や場所
告知方法には、就業規則への明記や個別の同意書、社内研修・説明会などがあります。
同意取得においては、従業員が監視内容を十分理解したうえで、自由意思に基づいて同意することが大切です。
強制的な同意のほか、同意しない場合の不利益な扱いはしないよう注意しましょう。
過度な監視によるモチベーション低下のリスク
パソコン利用監視ツールの導入は、適切に運用しなければ従業員のモチベーション低下を招く危険性があります。
従業員が「常に監視されている」と感じると、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 心理的ストレスの増大
- 創造性や自主性の低下
- 職場への不信感の醸成
- 離職率の増加
特に、監視の目的や範囲が不明確な場合、従業員は過度なプレッシャーを感じやすくなります。
信頼関係が損なわれると、業務効率の低下だけでなく、優秀な人材の流出にもつながりかねません。
このようなリスクを回避するためには、監視の目的と範囲を明確に説明し、必要最小限の監視に留めることが有効です。
また、監視データを改善提案に活用したり、定期的な意見交換の場を設けたりするのもよいでしょう。
監視ツールは、あくまで業務改善と情報セキュリティ強化のための手段です。
従業員の尊厳とプライバシーを尊重しながら、建設的な活用を心がけることが重要です。
監視データの適切な管理と保護
企業におけるパソコンの利用監視において、監視データの適切な管理と保護を実行するためには、以下の対応策が必要です。
| 対応策 | 詳細 |
|---|---|
| 保管期間の明確化 | ・監視ログの保存期間を社内規定で明文化する ・法的要件と業務上の必要性のバランスを考慮する ・不要なデータは定期的に削除する仕組みを構築する |
| セキュリティ対策の実施 | ・データの暗号化 ・アクセス制限 ・監査ログ |
| アクセス権限の管理 | 必要最小限の責任者に限定し、誰がいつデータにアクセスしたかを記録する |
| 従業員への透明性確保 | ・データの収集目的を明確に説明する ・保存期間と削除ポリシーを開示する ・プライバシーポリシーの策定と周知をおこなう |
これらの対策により、監視データの機密性を保ちながら、従業員との信頼関係も維持できます。
以下の記事では、企業のセキュリティ体制の強化について詳しく解説しています。
あわせてご覧ください。
企業のセキュリティ体制の強化方法一覧と具体例!最新アプローチも紹介
効果的な監視ツールの選び方

パソコンの利用監視ツールを選ぶときは、組織の規模と監視方法に応じた選定が重要です。
まず、監視する規模に応じてツールを選択しましょう。
| 監視規模 | 選択肢 |
|---|---|
| 小規模環境(数台~10台程度) | 無料ツールから始めることが可能。設定も簡単で、個別管理でも対応できる。ただし、将来的な拡張予定がある場合は、有償ツールの検討も必要 |
| 大規模環境(数十台以上) | 有料ツールの利用が推奨される。一括設定機能や可視化マップ機能が必須であり、安定性と拡張性を重視した選定が重要 |
また、監視方法による選択も検討すべきといえます。
詳細な情報収集が可能なエージェント型は、高度な監視が必要な場面に最適です。
一方、導入が簡単なエージェントレス型は、基本的な監視で十分な場面に適しています。
企業は組織のニーズと予算のバランスを考慮し、必要な機能を明確にしたうえで、最適なツールを選択することが大切です。
パソコンの利用監視で情報資産を守ろう

パソコンを利用監視するには、専門の監視ツールの導入が必要です。
一般的には、導入によりインターネットの使用状況や電子メールのほか、ソフトウェアの使用状況、キーロガー、ファイルとデータのアクセス、チャットログが確認できます。
ただし、監視するうえでは、従業員のプライバシー保護への配慮や過度な監視によるモチベーション低下のリスクなどに注意が必要です。
適切な監視により、企業の情報資産を守りましょう。
情報漏えい・ウイルス対策を強化したい場合は、ぜひ株式会社プラストのOA機器サービスをご利用ください。
さまざまなノウハウをもつ専門スタッフが、コンサルティングからシステム運用・メンテナンスまで、一貫したサービスとサポートをご提供いたします。
お気軽にお問い合わせください。

